北海道では、5月の端午の節句(こどもの日)に「べこ餅」を食べる習慣があります。
白と黒の2色の「べこ餅」は、「かしわ餅」とともに親しまれている、北海道民にはお馴染みの伝統和菓子です。
今回は、「べこ餅」についてご紹介します。
「べこ餅」とは?
「べこ餅」とは、白と黒の2色で木の葉の形に作られた餅菓子で、北海道では端午の節句に食べられる伝統和菓子です。

「べこ餅」は、上新粉を使用し、白色の生地は白砂糖、黒色の生地は黒砂糖を混ぜ合わせ、二つを組み合わせて木の葉の形に成形し、蒸し器で蒸して作ります。
木の葉の形が定番ではありますが、いまは丸い形や花の形をした「べこ餅」も作られています。地域によっては、あんこ入りの「べこ餅」を販売しているお店もあります。
黒い色のお餅には黒糖が使われているのでコクと風味のある味わい、白い色のあっさりとした味わいです。
この2色のバランスが味わい深さと、もっちりとした柔らかい食感が、子どもから大人まで親しまれています。
かしわ餅と同様に、こどもの日には欠かせないお菓子なんですよ。
「べこ餅」は北海道と青森県などの東北の一部の郷土菓子ですが、北海道と東北では形や色合いが違っています。青森県の下北半島に伝わる「べこもち」「べごもち」は、かまぼこのような形に作られ、そのお餅を切ると金太郎飴のようにきれいな模様が現れます。現代風にアレンジしている「べこもち」も多く、かわいいアニメや動物のキャラクターの「べこもち」も作られています。
北海道と東北、地域によって作り方も形も違うんですね。下北半島で作られている「べこもち」は、とても手間が掛かっているように感じました。
「べこ餅」は山形県の郷土菓子の「くじら餅」を北海道で独自に変化させ、独特の木の葉型になったといわれているんですよ。
「べこ餅」と「くじら餅」の味の違いを実際に試してみたくなりますね。
「べこ餅」の名前の由来は?
「べこ餅」に名前の由来には、諸説あります。
1.黒糖を加えたお餅の黒い部分がべっ甲の色合いに似ている
2.原料に「米粉(べいこ)」を使っているので、”べいこ餅”から変化した
3.白と黒の2色が乳牛のホルスタインに似ているので、牛を意味する”べこ”からついた
など...
私は、3の牛の模様に似ている”べこ”説を聞かされてきていて、ほのぼのした由来でかわいいなと思っていました。諸説が色々あるとは驚きでした。
どれが本当の由来なんでしょうね。
「べこ餅」を端午の節句に食べるのはなぜ?
「べこ餅」の発祥となった「くじら餅」が、お祝い事の際に食べるという習慣を引き継ぎ、端午の節句に食べられるようになったといわれています。
また、私は「牛のようにたくましく、物事に動じず、勤勉な人になるように」という願いが込めて、端午の節句に食べられているとも教わりました。
いまは、和菓子屋さんで季節を問わず販売しているお店も多く、端午の節句の他、お正月やお彼岸、冠婚葬祭などハレの日の際にも食べられています。
昔は「べこ餅」の木型を使って家庭で親子が一緒につくることも多かったのですが、いまは手軽に購入することができるようになりました。
「べこ餅」のレシピと作り方
「べこ餅」はとても簡単に作れます。
木型が無くても木の葉の形は作れますし、お好きな形にアレンジしても楽しいですね。
材料(10個分)
作り方
「べこ餅」」の通販は六花亭と野島製菓がおすすめ
北海道以外では見かけることがない「べこ餅」ですが、通信販売で購入することができます。
六花亭の「べこ餅」は木の葉の形ではなく、まるっとしたかわいい形をしています。

画像元:六花亭公式ホームページ
国産の黒糖の風味ともっちりとしたこしのある「べこ餅」です。1個108円(税込)とリーズナブルなのもうれしいですね。5月前期の通販おやつ屋さんにもラインナップされていますよ。
小樽市の野島製菓の「べこ餅」は、北海道の伝統そのままの木の葉の形をしています。
沖縄の最高級黒糖を使用した素朴な味わいの「べこ餅」のほか、よもぎ餅と白いお餅の組み合わせもあります。
独自の密着包装と熱殺菌処理のおかげで、賞味期限が長いのもうれしいですね。
北海道の端午の節句に欠かせない伝統和菓子「べこ餅」は、素朴で懐かしい味がしますよ。
ぜひ一度食べてみていただきたい一品です。
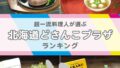

コメント